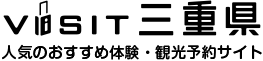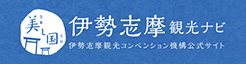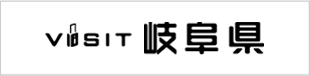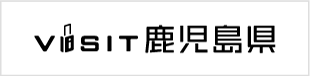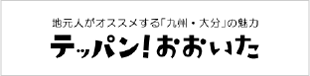<伊勢市内周遊観光バス> ”美し国周遊ばす”伊勢神宮両宮参拝プラン
全国各地から訪れる参拝者で賑わいを見せる伊勢神宮ですが、時間やスケジュールの都合から内宮だけ参拝して帰ったという話もよく聞きます。お伊勢参りは外宮から内宮の順にお参りするのが古くからのならわしです。
外宮と内宮をガイド付きで参拝出来て、さらに、周辺の見どころやグルメも楽しめる着地型バスツアー、「美し国(うましくに)周遊ばす」をVISIT取材班(以下、取材班)がレポートします!
(本レポートは取材当時に基づいています。記事の内容には一部古い情報が掲載されています)
「美し国周遊ばす」は完全予約制。「式年遷宮記念号」は、前日の18時まで予約可能です。この日は、近鉄宇治山田駅前乗り場から乗車(11:05)しました。レトロな駅舎内にある窓口で受付をし、ツアー参加券と引き換えに、プランの利用ガイドとクーポン券を受け取ります。
受付窓口の前にある乗り場からバスに乗り込みます。ゆったりとしたシートに落ち着くと同時に、じわじわと旅行気分がこみ上げてきた取材班。ナビを頼りに自ら車を運転し、目的地へ急ぐ普段の取材とは大違いです。早くもくつろぎモードの取材班を乗せて、バスは、JR・近鉄伊勢市駅乗り場を経由して、最初の目的地「伊勢神宮・外宮」に向かいます。市街地に接している外宮は、内宮に比べると小ぢんまりとした印象を受けますが、一歩神域に足を踏み入れると、凛とした空気が漂います。
写真は、神楽殿の前を通り過ぎるところ。駐車場から表参道火除橋(おもてさんどうひよけばし)を渡り、手水舎(てみずしゃ)で心身を清め、神楽殿の前までゆっくり歩いて約10分というところです。
外宮は、天照大御神(あまてらすおおみかみ)の食事を司る神様、豊受大御神(とようけおおみかみ)をお祀りしています。豊受の「受」は食物を意味し、衣食住をはじめ、あらゆる産業の守り神として尊崇を集めています。建物は、内宮と同じ唯一神明造(ゆいいつしんめいづくり)ですが、屋根の鰹木(かつおぎ)が9本(内宮より1本少ない)で、千木(ちぎ)の先端が垂直に切られているなど、細部に違いがあるそうです。
外宮から約15分でバスは内宮に到着。昼食付きのプランで参加している取材班は、昼食会場の「勢乃國屋」に向かいます。内宮の宇治橋前に明治から店を構える老舗のお土産物店です。さらに「美し国周遊ばす」のゲストには、お土産物が10%割引になるサービスがあり、嬉しい限り♪ 1階には、伊勢・鳥羽・志摩の観光案内カウンター「美し国観光ステーション」が併設されており、旬の情報やお得な情報を手に入れることが出来ます。
楽しみの昼食は、内宮の杜を望む2階のレストラン。ガイドさん同行の内宮参拝(希望者のみ)の集合場所も勢乃國屋なので、ゆっくり、安心していただく事が出来ました。
伊勢御膳 ※9月30日まで

てこね膳島路※10月1日から
昼食付きのプランで味わえるのは、伊勢志摩の名物を合わせた「伊勢御膳またはてこね膳島路」!ご当地グルメの超定番「伊勢うどん」と「手こねずし」に、4種類の小鉢と味噌汁、香の物が付いています。ボリュームもほどよく、これなら内宮参拝の後、食べ歩きも楽しめそうですね!(写真はイメージ)
食べ終わったら、いざ、内宮参拝へ! 内宮の表玄関・宇治橋鳥居から御正宮(ごしょうぐう)までは、ゆっくり歩いて約20分。心を静めて神様の前に出るための大切なアプローチではありますが、昼食後の腹ごなしにもちょうどいい距離だなぁと思ってしまう、ちょっと不謹慎な取材班なのでした。
手水舎でガイドさんからお清めの作法を教わりました。
①まず右手でひしゃくを持ち、水を汲んで左手を洗います。
②ひしゃくを左手に持ち替え、右手を洗います。
③ひしゃくを右手に持ち替え、左の手のひらに水を受け、口をすすぎます。
④すすぎ終えたら、もう一度左手を洗います。
⑤最後にひしゃくを垂直に持ち上げ、ひしゃくの水を柄に伝わせるようにこぼし、ひしゃくを洗います。
マナーという観点からも、ぜひ覚えておきたい作法ですね。
(参照:伊勢神宮公式HP 参拝の作法とマナー)
神楽殿の前を通り、天照大御神がお座す御正宮が見えてきました。2000年の時を超えて、古代の佇まいを現在に伝えています。撮影が許されるのはこの階段の下まで。参拝の作法は「二礼二拍手一拝」。取材班も気持ちを切り替えて、しっかりとお参りをさせていただきました。
内宮参拝の後は、「おはらい町」と「おかげ横丁」で約1時間のフリータイム。宇治橋前から約800メートル続く門前町を「おはらい町」、その中ほどにある赤福本店を中心にした一画が「おかげ横丁」といわれています。江戸から明治の町並みが再現されたおかげ横丁には、名物から人情まで伊勢路の魅力がいっぱい! 事前に観光サイトやガイドブック等で、行きたいお店をチェックしておくのが賢いかもしれませんね。
プランには「神代餅と伊勢茶のおもてなし」も付いています。神代餅は、保存料・着色料を一切使用していない昔ながらの草餅で、口に入れると、よもぎの香りがふんわり鼻の奥をくすぐります。添えられた伊勢茶もすっきりとした味わいで、神代餅の素朴な甘さとよく合っていました。神代餅と伊勢茶は、勢乃國屋直営の茶店「茶房太助庵」でいただくことができます。御幸道路沿いにある茶房は、昭和初期に建てられた倉庫をリノベーションした、レトロモダンな雰囲気。店内に飾られた当時の調度品や食器も素敵です♪

神代餅と伊勢茶でほっこりした取材班は、再びおかげ横丁へ。取材とはいえ、ここはしっかりと観光客気分を満喫せねば! おかげ横丁でのお土産選びは、まるで宝探し♪ そんな取材班の目に留まったのは、おかげ犬のおみくじ(写真・300円)。その昔、ご主人の代わりにお伊勢参りをしたといわれている、おかげ犬。いろいろな人に助けられながら、お伊勢参りを成し遂げたおかげ犬に、取材班もぜひあやかりたいものです!
続いては、彦大御神を祀る“猿田彦神社”をお参りします。
続いて、猿田彦神社を参拝します。猿田彦大御神は天孫降臨の際に、高千穂に瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を御案内した神様ということで物事を良い方向へと導く“みちひらきの神様”とも言われております。
物事の始まりの際には道標となってくれる神様として、昔から信仰されてきた神様です。
また、建築・方位除け・災難除け・開運・事業発展・五穀豊穣・大漁満足・家内安全・交通安全・海上安全など、古来多くの御神徳で知られています。
猿田彦神社の境内には昭和11年まで御本殿があった跡地に、八角で方位が刻まれている石柱があります。
刻まれている方位は『十干十二支(じゅっかんじゅうにし)』で記されていて、
猿田彦大神が長くご鎮座されていた神聖な場所として、多くの方々が石柱を触られているというパワースポットです。
猿田彦神社参拝の後は、内宮 別宮の月讀宮を参拝します。月讀宮は、照大御神の弟神にあたる月讀尊(つきよみのみこと)、お父さんにあたる伊弉諾尊(いざなぎのみこと)お母さんにあたる伊耶那岐命(いざなみのみこと)、月讀荒御魂宮( つきよみのあらみたまのみや)、がお祀りされているお宮で、内宮別宮としては天照大神の魂を祭神とする荒祭宮(あらまつりのみや)に続いて位の高いお宮として知られております。
外宮から始まったお伊勢参りもあっという間に終わり、バスは取材班が泊まる宿がある鳥羽のバスセンターに到着。この一日ですっかり顔なじみになった、運転手さんともここでお別れです。
「伊勢神宮両宮参拝プラン」、いかがでしたでしょうか。
いまいち自信のなかったお伊勢参りや駐車場を探す手間もなくて楽々。外宮と内宮の両参りに、町歩きやグルメも楽しめる!今時のお伊勢参りに出かけてみませんか?
【情報】乗車地は「伊勢市駅前」「宇治山田駅前」「鳥羽バスセンター」
降車地は「伊勢市駅前」「宇治山田駅前」「夫婦岩東口」「鳥羽バスセンター」から選べます。
電話でのお申し込みの場合は、前日18:00までご予約承ります。

名古屋名鉄バスセンターを出発し伊賀上野まで皆さまをお連れする、毎日1名から運行の日帰りバスツアー!

高速バスで上野市駅に到着後、だんじり会館内伊賀上野観光協会にてクーポン券を引き換えます
(だんじり会館内伊賀上野観光協会へのアクセスはこちら)
※7/19以降は旧上野市庁舎 SAKAKURA BASE 1階の伊賀市観光インフォメーションセンターとなります。詳細はこちら)
 伊賀流忍者博物館は伊賀の土豪屋敷を上野公園内に移築したもので、外観はごく普通の茅葺きの農家に見えますが、屋敷のあちこちに防衛のためのしかけや、屋敷内にはドンデン返し、仕掛け戸、もの隠しなどが施された忍者屋敷なのです!
伊賀流忍者博物館は伊賀の土豪屋敷を上野公園内に移築したもので、外観はごく普通の茅葺きの農家に見えますが、屋敷のあちこちに防衛のためのしかけや、屋敷内にはドンデン返し、仕掛け戸、もの隠しなどが施された忍者屋敷なのです!

忍者伝承館では本物の忍具が展示されており、忍者の歴史を知ることができます。

また、忍術体験館では手裏剣体験ができます(プランBには料金が含まれています)忍者の衣装姿で体験すれば、本物の忍者の気分を味わえるかも!?

また、博物館では忍者ショーも開催されており、こちらも人気です(別途300円必要。開催日は要確認)

伊賀流忍者博物館と同じ上野公園内にあるのが俳聖殿(はいせいでん)です(入館無料)芭蕉の旅姿を形どった八角堂で、殿内には伊賀焼等身大の芭蕉座像を安置しています(芭蕉座像公開は芭蕉祭の10月12日のみ)

伊賀上野城は別名「白鳳城」と呼ばれる美しい城で、内堀の石垣は、藤堂高虎が築いたもので高さが約30メートルあり日本一と言われています。
上野公園内には、上野城、俳聖殿、忍者屋敷など名所・旧跡がたくさんあり、趣き豊かな歴史の風情をたっぷりと残しています。四季折々の景観が楽しめるのも魅力のひとつです。
「かたやき」は忍菓と呼ばれ伊賀忍者の非常食でした。日本一硬いといわれるお煎餅で、ほどよい甘さと芳しい香りのする素朴な伊賀を代表する銘菓です。

「丁稚(でっち)ようかん」は昔から伊賀地方で親しまれてきた伝統銘菓で、水ようかんよりも甘さ控えめで、噛まなくても食べれる柔らかいようかんです。丁稚ようかんの名前の由来は諸説ありますが、江戸時代に丁稚が練りようかんを作った後、鍋に残ったようかんに水を混ぜ、水ようかんのようにしたものを丁稚さんが好んで食べていたことから「丁稚ようかん」と呼ばれるようになったといわれています。
伊賀上野観光の中心である上野公園を中心に、フリータイムで伊賀上野をたっぷり楽しめる日帰りバスツアーです。ぜひ忍者の衣装に着替えて忍者姿で伊賀上野の町を楽しみましょう!
卍 伊賀流忍者とは 卍
画像をクリック(伊賀流忍者博物館HP)
〔関連動画〕 ![]() にんじゃチャンネル【伊勢忍者キングダム】
にんじゃチャンネル【伊勢忍者キングダム】
~村内花魁道中~ (過去に実施した花魁道中の動画)